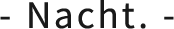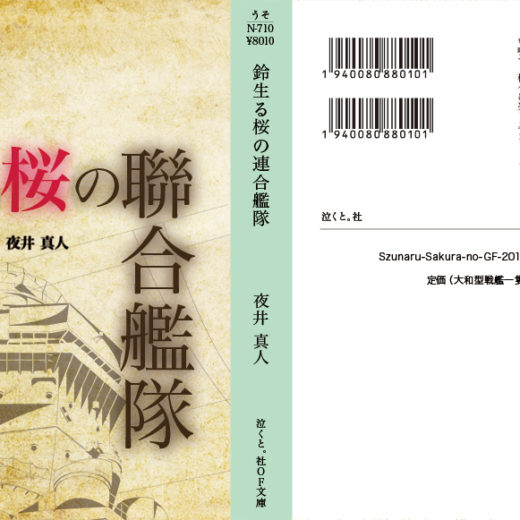先週、名古屋フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会に行ってきました。
もともとクラシックに興味があったんですが、プロの生オーケストラの演奏って聴いたことないよね!?と思い立ったが即行動。チケットを買って友人と行ってきました。
「愛の喜びと悲しみ」というテーマのもと、ポーランドの巨匠アントニ・ヴィット先生が指揮するシューマンとチャイコフスキーの曲を聴いてきました。クラシック初心者ですが、色々良すぎた~。
シューマン:序曲『ヘルマンとドロテア』作品136
ところでこの演奏会の前にシューマンという音楽家の生涯について予習したんですよ。『子どものためのアルバム』『トロイメライ』なんかが有名ですけどほとんど聴いたことがなかったので。
間違いなく彼は音楽の才能がある人だったのだと思います。そして彼が音楽と愛する家族のことだけ考えていられたらどんなによかったでしょう。
ゲーテの叙事詩に心を寄せ、精神的な摩耗に苦しみながらも作曲されたのがこの序曲『ヘルマンとドロテア』になります。
情緒豊かで牧歌的なのどかさとフランス革命という動乱の時代の雰囲気をうかがわせる奥行きがある曲なんですが、これがたったの数時間で作曲されたってマジ…!?もし何も知らずに聴いていたら「さぞかし絶好調なときに出来上がった曲で初演とかすごい反響だったんだろうな」と思わせるような、なんといったらいいのか、現代でもわかる当時の名曲という風格です。これで序曲だけ(つまり歌劇等にする構想があった)というのですから……シューマンが思い描いてたとおりのことが全部実現されたらどんな様相になっていたのか想像するのも楽しいですね。
シューマン:ヴァイオリン協奏曲ニ短調
ヴァイオリン協奏曲なのでソリストの方がいらっしゃったんですが、ヴァイオリンがあまりにも巧すぎる……(あたりまえ体操)
◆第一楽章 力強く、早すぎないテンポで
そもそもこの曲ってヴァイオリニストのヨーゼフ・ヨアヒムの演奏に甚く感銘を受けたシューマンが作曲してるんですが、初演が作曲から80年後だったんですよね。ヨアヒムはこれを弾くことはなかったそうなので。
シューマンの晩年も晩年に作られた曲だからか、彼の苦悩に満ちた人生をなぞるような物憂げな旋律が印象的でした。
ただ、第一楽章の終わりには曇り空のすき間から天使のはしごが下りてくるような、希望を感じられるような景色で終わります。ロマン派っぽい!!(ロマン派っぽいとは?)
◆第二楽章 ゆるやかに
◆第三楽章 生き生きと、しかし速くなく
シューマンの人生って私から見たら特に後半は苦悩に満ちているんですが、それはそれとして彼が愛情深い人間なんだろうなぁということも曲を聴いていたらよくわかります。
公演が終わってから友人と感想戦をやっていたんですが、第二楽章~について私も友人も「めっちゃ嫁と家族のこと考えて書いてたよな、きっと」と意見が一致しました。実際シューマンは愛妻家かつ子どもたちを愛していたそうな。
この曲を聴いているときに、シューマンの奥さんでピアニストのクララがシューマンの今際の際の抱擁について「世界中の宝をもってしても、この抱擁にはかえられないでしょう」という言葉を残したことを思い出して泣いてしまいました。
人の愛情に訴えかけてくるような、奥ゆかしさがある素敵な曲でした。
あとこの曲のソロ、けっこう忙しなくいったりきたりする旋律があって、短い音の中にある揺らぎみたいなのが心地よくて好きでした。
ソリスト・アンコールはシューマンがクララに捧げた『ミルテの花:献呈』。
ヴァイオリンの重音がまるで寄り添う夫妻のようで本当に素晴らしい曲でした。
チャイコフスキー:幻想曲『フランチェスカ・ダ・リミニ』
さて、シューマンの曲が終わり20分の休憩をはさんだらチャイコフスキーの時間。 とはいえ私はチャイコフスキーの曲はバレエ音楽の有名なものしか分からず、『フランチェスカ・ダ・リミニ』のタイトルを見てもピンと来ていませんでした。
公演パンフレットに書いてあったのですが、こちらの曲はダンテの『神曲』《地獄篇》第5歌をもとに作られた曲となっています。第一部は地獄で人々が苦しむ様子、第二部で罪を犯すフランチェスカと、その結婚相手ジョヴァンニの弟のパオロの恋の様子、第三部で密会がバレてジョヴァンニの怒りにより殺された二人が罪人として地獄に落ちる様子が描写されています。
この曲が一番すごかった。公演が終わった後も延々この曲のことを考えて、なんならこれを書いている今もなお聴いている。
第一部と第三部の地獄の描写は「燃えている~~~!!!!」「トゲトゲの山~~~!!!!(?)」「嵐が吹き荒んでいる~~~!!!!」みたいな、イメージしているとおりの(キリスト教圏の)地獄が音楽で聴ける感じです。とにかく打楽器の迫力がすごくて怖かった。構成的にもチャイコフスキーの盛り上げ上手さが痛いくらいに伝わった一曲です。弦楽器も弓がぶちぶち切れてたりした。友人も「ヴァイオリンの音が完全に亡者の悲鳴だったわ……」と言っており、「それだ~」と唸っていました。
第二部は木管中心にロマンチックで素敵な、でも悲しい結末が待っている恋といった雰囲気の旋律が続くのですが、パンフには『ホルンの介入によって場が一変し~』と書かれていたので、金管の人たちが構えるたびに気が気じゃなかったですね。
神曲の地獄ってギリシャ神話の冥界がもとになっているんですが、冥界ってハデス様そのものなので「これがチャイコフスキーの思うハデス様かぁ」と思ったりもしました。
この曲25分くらいあるのですが、地獄に圧倒されていたら本当に本当にあっという間に時間が過ぎました。カッコいい曲です。
チャイコフスキー:幻想曲『ロメオとジュリエット』
いわずと知れたシェイクスピアの恋愛悲劇『ロミオとジュリエット』をもとに作曲された序曲。
ロミオとジュリエットがたどる悲劇的な結末を我々は知っているわけで、モンタギュー家とキャピュレット家の対立を表すような不穏さとか威厳みたいな厳しさがあるのに、これがまたところどころ恋の波動を感じる良い雰囲気になるんですよね。どんな顔して聴いたら良いの、本当に?
二人の死はモンタギュー家とキャピュレット家に和平をもたらし、曲も大団円で終わります。
演奏が終わったあとは一本の名作映画を観終わったような満足感で、チャイコフスキーは題材がある曲を作るのがめちゃうまいのでは…!?と思いました。
私が知っていたチャイコフスキーは『白鳥の湖』とか『くるみ割り人形』なんですが、上記二曲を聴いて「本当に『花のワルツ』と同じ作者が書いた曲なのか……?」と、そのギャップに飲み込まれることになりました(ちなみに白鳥の湖やくるみ割り人形よりも『フランチェスカ・ダ・リミニ』と『ロメオとジュリエット』のほうが先に作曲されている)
コンサートに行ってみて、やっぱり生で聴くオーケストラって良いなぁ~!すごく良い!!と思いました。
また行きたいです!!
来年はぜひ、第九を生で!!